浜離宮恩賜庭園

|
|
もと徳川将軍家の鷹狩場であったところを、承応3(1654)年、4代将軍徳川家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が埋め立てて、甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を建てたのが始まり。 その後、綱重の子綱豊(家宣)が6代将軍になったときに将軍家別邸となり、浜御殿と呼ばれるようになった。以後将軍が変わる都度改修が加えられ、11代将軍家斉の時にほぼ今のような姿になったという。 海水を引き入れた潮入りの池と庚申堂、新銭座の二つの鴨場を持つ総面積25万㎡のこの庭園は、江戸城の出城の機能も果たしていたという。慶応4(1868)年、鳥羽伏見の戦いに敗れ、大阪を逃れた最後の将軍徳川慶喜が江戸に帰って上陸したのもここである。 明治維新後は皇室の離宮となり、園内にあった延遼館が迎賓館として多くの外国の貴賓客をもてなす場となっていた。 戦後東京都に下賜され、昭和21年4月から浜離宮恩賜庭園として公開された。 昭和27年11月には「旧浜離宮庭園」として国の特別名勝及び特別史跡に指定された。 |

|
|
大手門橋 築地川に架かる大手門橋を渡ると桝形。重厚な石垣は大手門の跡。ここが庭園の正面入り口となっている。 |
 |
|
三百年の松 門を入って左から南へ回ると行く手左に大きな松がある。 約300年前、6代将軍家宣が庭園を大改修したときに植えた松という。太い枝が地面すれすれに横たわるように伸ばしている姿は十分貫禄がある。都内でも最大級の黒松という。 |
 |
|
お花畑 南へ内堀を渡るとお花畑が広がる。春はナノハナが、秋にはキバナコスモスがそれぞれ30万本咲き乱れ、その見事さは都心にいることお暫し忘れさせてくれる。 園内には他にウメ、サクラ、ボタン、ハナショウブなどの花が咲き、四季折々の花を楽しむことができる。 |
 |
|
旧稲生神社 お花畑を過ぎると旧稲生神社がある。創建や祭神は不明であるが、江戸時代後期の絵図には別の場所に稲荷社が描かれていることから、古くから園内にあったことが伺える。現在の建物は明治27年の東京湾を震源とする地震で倒壊したものを翌年再建し、その後何度か修理したのち、平成17年に大修理をしたもの。内部に江戸時代後期の宮殿がある。今は建物だけとなっている。 |
 |
|
将軍お上がり場 旧稲生神社の裏手が梅林になっている。季節なら馥郁たる香りを楽しみながら進むと左に水上バスの発着所を見てすぐ先が東京湾。 ここが船着き場で、将軍が江戸城から船で来るときはここで乗下船していた。最後の将軍慶喜が大阪を脱出し、江戸に戻ったときもここから上陸したという。 この先ベンチがたくさん並んでいるので、気候の良いときはのんびり水鳥を見ながらお弁当を広げるのもよい。 |
 |
|
潮入の池 庭園の中心となる池。海水を直接引き入れた池で、潮の干満による水位の上下によって池の趣を変える仕組みになっている。海辺の庭園で多く用いられていた様式で、旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、旧安田庭園などもかつては潮入の池だったが、現在実際に海水が出入りしているのはここだけ。 |
 |
|
横堀水門 東京湾から潮入の池への海水はここから引き入れている。潮の干満による水位の上下をここで調整している。 |
 |
|
中島のお茶屋 潮入の池の中に浮かぶ島にあるお茶屋。宝永4(1707)年に建てられた休憩所。将軍はじめ奥方や公家たちがここで茶を喫しながら庭園の眺望を楽しんだのだろう。当時の建物は、昭和19年の戦災で焼失し、昭和58年に再建されたもの。 ここでは抹茶・お菓子をいただきながら休憩ができる。 |
 |
|
お伝い橋 池の両岸から中島にかけられた橋。現在の橋は、平成24年に改修されたもので総檜造り。長さ118mある。 |
 |
|
松の御茶屋 中島の御茶屋のほかに松の御茶屋、燕の御茶屋が池に面して建てられている。いずれも昭和19年の戦災で焼失していたが、平成22年に松の御茶屋が、平成27年に燕の御茶屋が復元された。 |
 |
|
鴨場の小覗
|
 |
|
鴨場の引掘 鴨猟の仕方(現地案内板より) |
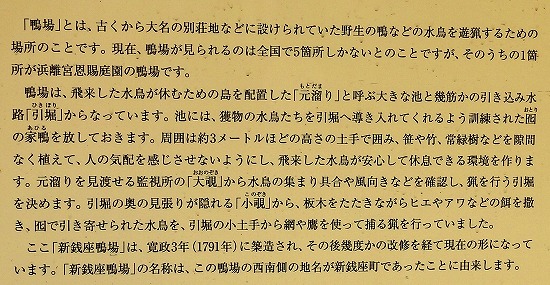 |
 |
|
所在地 東京都中央区浜離宮庭園1-1 アクセス JR新橋駅から徒歩12分 浅草から隅田川を下る水上バスも良い 35分 740円 入園料 300円 65歳以上150円 休園日 年末年始(12/29~1/1) 開園時間 9時~17時(入園は16時30分まで) |
ホーム トップ